男性で高い肝細胞がん有病率の分子機序を解明 [癌の分子医学]
カリフォルニア大学サンディエゴ校のWillscott E. Naugler博士らは、肝細胞がん(HCC)の有病率が女性よりも男性で高い理由の根拠となる分子機序をScience(317: 121-124)に発表した。この機序には、女性がエストロゲンから得る保護作用が関連している。

<DENへの曝露でIL-6産生促進>
男性が女性よりもHCCの有病率が高い理由として、男性ではB型肝炎ウイルス(HBV)/C型肝炎ウイルス(HCV)に感染する可能性やアルコール乱用/喫煙の可能性が高いことが挙げられるが、遺伝やホルモンに関与する因子も影響を及ぼしている。
Naugler博士らは「マクロファージの1種であるクッパー細胞(KC)によるインターロイキン(IL)-6産生が、エストロゲンの介入により阻害されるため、女性では肝がんリスクが低下する」と述べている。
同博士らはこの知見は将来、臨床上の進歩につながると推測し、「今回の知見を利用して男性のHCCを予防できる可能性がある」としている。 同博士らは、ヒトのHCCに特徴的な性差が、化学発がん物質であるジエチルニトロサミン(DEN)を投与したマウスに見られる性差と一致するという事実を研究の始点とした。DEN投与により、雌マウスよりも雄マウスで炎症誘発性サイトカインである血中IL-6値がより大幅に上昇することが明らかになった。
しかし、マウスでIL-6を阻害すると、HCCの性差は消失した。IL-6を阻害した結果、雄マウスの肝がん発生率は約90%低下したが、雌マウスの肝がん発生率に有意な影響はなかった。
DENへの曝露がKCでのIL-6産生を促進する機序には、小型のアダプター蛋白質である骨髄分化因子88(MyD88)への依存性が伴う。MyD88はToll様受容体によるシグナリングに関与する。MyD88の阻害が、DEN誘発肝がんの発生から雄マウスを保護するもう1つの経路であることが明らかになった。
<エストロゲンの保護作用>
Naugler博士らは、Japanese Journal of Cancer Research(92: 249-256)に発表された研究から、雄マウスのHCC発生率は去勢とエストロゲン投与の双方により低減することを認識していた。
エストロゲンによるこの保護作用の根拠となる分子機序を解明したのは、同博士らの業績である。同博士らの研究により、DENに曝露した後、雄マウスのALTが上昇し、肝細胞のアポトーシス率が増加し、肝細胞の増殖が促進されることが明らかになった。ALTの上昇は肝細胞損傷の指標である。
しかし、エストロゲン投与により、雄マウスのALTは雌マウスと同等まで低下した。さらに、卵巣を切除された雌マウスのALTは雄マウスと同等であった。この結果は、エストロゲンが肝損傷に大きな影響を及ぼすことを示している。
同博士らは、雄のIL-6ノックアウトマウスでは、DEN投与によるHCCの発生率が低下し、生存オッズ比が大幅に増加することを明らかにした。また、IL-6の発現はMyD88に依存的であることを実証した。MyD88欠損雄マウスがDENに曝露してもHCCは発生しなかった。
KCが肝臓から分離された場合、壊死した肝細胞に曝露したKCからのIL-6分泌はエストロゲン投与により阻害された。また、エストロゲンはDENを前投与した雄マウスのIL-6循環濃度を低下させた。これは、エストロゲンが媒介となってKCによるIL-6産生を抑制したために雌マウスの発がんリスクが低下したことを示唆している。
<HCC予防法発見に期待>
ブラウン大学のJack Wands博士は、基礎研究で得られた重要な成果の臨床的意義をNew England Journal of Medicine(2007; 357: 1974-1976)に発表し、「細胞レベルでは、KCが中心的役割を果たすと思われる。KCはToll様受容体を用いて壊死残片を検知し、同受容体はメッセンジャー分子であるMyD88を介して細胞核にシグナルを伝達する。これによりIL-6産生の上方制御が生じるが、その事象はエストロゲンにより阻害される。IL-6値の上昇はHCC発生の一因となる」と説明している。
同博士は、既知の過程として「ウイルス抗原に対する宿主の炎症性免疫反応が肝細胞の損傷を誘発し、その後、肝細胞が再生して線維化や肝硬変を発症するが、これらはHCCの発生病理における重要な特徴である」と説明している。エストロゲンがその保護作用を働かせるのはこの過程内である。
ここで問題となるのは、臨床における今回の研究の意義である。同博士は「高リスク男性におけるIL-6のメッセンジャーRNA(mRNA)や蛋白質の濃度が女性と比べて高いことは、エストロゲンやエストロゲン様化合物がヒトにとって予防薬となる可能性を示唆するのであろうか。当然この疑問から、エストロゲンやエストロゲン様化合物による療法が肝臓系、心血管系と内分泌系に有害作用を及ぼす可能性についての懸念が生じる」と指摘。「一方、HBVやHCVの複製を抑制し、その持続感染を根絶する抗ウイルス療法はHCCの予防に大きな効果を示す可能性があり、研究を進めるべきである」と示唆している。
HCCの問題が、特定の地域でより深刻であることが知られている。同博士は「例えば、男性における有病率、および有病者に占める男性の比率はアジア・太平洋地域で高い。慢性HBV感染は他の地域よりもこの地域で多い」としている。
Naugler博士は「乳房など明らかに性の影響を受ける器官もあるが、肝臓などは影響を受けない。したがって、肝炎がエストロゲンにより顕著に抑制されることはきわめて興味深い。通常は性と関連のない器官が、同様の原理により制御される可能性が高まる。例えば、膀胱がんの罹患率は女性よりも男性で高い。その差異は男性の膀胱における高いIL-6値と炎症の結果生じるのであろう」と解説した。MT 08年3月6日(VOL.41 NO.10) p.11]

<DENへの曝露でIL-6産生促進>
男性が女性よりもHCCの有病率が高い理由として、男性ではB型肝炎ウイルス(HBV)/C型肝炎ウイルス(HCV)に感染する可能性やアルコール乱用/喫煙の可能性が高いことが挙げられるが、遺伝やホルモンに関与する因子も影響を及ぼしている。
Naugler博士らは「マクロファージの1種であるクッパー細胞(KC)によるインターロイキン(IL)-6産生が、エストロゲンの介入により阻害されるため、女性では肝がんリスクが低下する」と述べている。
同博士らはこの知見は将来、臨床上の進歩につながると推測し、「今回の知見を利用して男性のHCCを予防できる可能性がある」としている。 同博士らは、ヒトのHCCに特徴的な性差が、化学発がん物質であるジエチルニトロサミン(DEN)を投与したマウスに見られる性差と一致するという事実を研究の始点とした。DEN投与により、雌マウスよりも雄マウスで炎症誘発性サイトカインである血中IL-6値がより大幅に上昇することが明らかになった。
しかし、マウスでIL-6を阻害すると、HCCの性差は消失した。IL-6を阻害した結果、雄マウスの肝がん発生率は約90%低下したが、雌マウスの肝がん発生率に有意な影響はなかった。
DENへの曝露がKCでのIL-6産生を促進する機序には、小型のアダプター蛋白質である骨髄分化因子88(MyD88)への依存性が伴う。MyD88はToll様受容体によるシグナリングに関与する。MyD88の阻害が、DEN誘発肝がんの発生から雄マウスを保護するもう1つの経路であることが明らかになった。
<エストロゲンの保護作用>
Naugler博士らは、Japanese Journal of Cancer Research(92: 249-256)に発表された研究から、雄マウスのHCC発生率は去勢とエストロゲン投与の双方により低減することを認識していた。
エストロゲンによるこの保護作用の根拠となる分子機序を解明したのは、同博士らの業績である。同博士らの研究により、DENに曝露した後、雄マウスのALTが上昇し、肝細胞のアポトーシス率が増加し、肝細胞の増殖が促進されることが明らかになった。ALTの上昇は肝細胞損傷の指標である。
しかし、エストロゲン投与により、雄マウスのALTは雌マウスと同等まで低下した。さらに、卵巣を切除された雌マウスのALTは雄マウスと同等であった。この結果は、エストロゲンが肝損傷に大きな影響を及ぼすことを示している。
同博士らは、雄のIL-6ノックアウトマウスでは、DEN投与によるHCCの発生率が低下し、生存オッズ比が大幅に増加することを明らかにした。また、IL-6の発現はMyD88に依存的であることを実証した。MyD88欠損雄マウスがDENに曝露してもHCCは発生しなかった。
KCが肝臓から分離された場合、壊死した肝細胞に曝露したKCからのIL-6分泌はエストロゲン投与により阻害された。また、エストロゲンはDENを前投与した雄マウスのIL-6循環濃度を低下させた。これは、エストロゲンが媒介となってKCによるIL-6産生を抑制したために雌マウスの発がんリスクが低下したことを示唆している。
<HCC予防法発見に期待>
ブラウン大学のJack Wands博士は、基礎研究で得られた重要な成果の臨床的意義をNew England Journal of Medicine(2007; 357: 1974-1976)に発表し、「細胞レベルでは、KCが中心的役割を果たすと思われる。KCはToll様受容体を用いて壊死残片を検知し、同受容体はメッセンジャー分子であるMyD88を介して細胞核にシグナルを伝達する。これによりIL-6産生の上方制御が生じるが、その事象はエストロゲンにより阻害される。IL-6値の上昇はHCC発生の一因となる」と説明している。
同博士は、既知の過程として「ウイルス抗原に対する宿主の炎症性免疫反応が肝細胞の損傷を誘発し、その後、肝細胞が再生して線維化や肝硬変を発症するが、これらはHCCの発生病理における重要な特徴である」と説明している。エストロゲンがその保護作用を働かせるのはこの過程内である。
ここで問題となるのは、臨床における今回の研究の意義である。同博士は「高リスク男性におけるIL-6のメッセンジャーRNA(mRNA)や蛋白質の濃度が女性と比べて高いことは、エストロゲンやエストロゲン様化合物がヒトにとって予防薬となる可能性を示唆するのであろうか。当然この疑問から、エストロゲンやエストロゲン様化合物による療法が肝臓系、心血管系と内分泌系に有害作用を及ぼす可能性についての懸念が生じる」と指摘。「一方、HBVやHCVの複製を抑制し、その持続感染を根絶する抗ウイルス療法はHCCの予防に大きな効果を示す可能性があり、研究を進めるべきである」と示唆している。
HCCの問題が、特定の地域でより深刻であることが知られている。同博士は「例えば、男性における有病率、および有病者に占める男性の比率はアジア・太平洋地域で高い。慢性HBV感染は他の地域よりもこの地域で多い」としている。
Naugler博士は「乳房など明らかに性の影響を受ける器官もあるが、肝臓などは影響を受けない。したがって、肝炎がエストロゲンにより顕著に抑制されることはきわめて興味深い。通常は性と関連のない器官が、同様の原理により制御される可能性が高まる。例えば、膀胱がんの罹患率は女性よりも男性で高い。その差異は男性の膀胱における高いIL-6値と炎症の結果生じるのであろう」と解説した。MT 08年3月6日(VOL.41 NO.10) p.11]














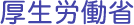




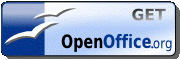




コメント 0